日本とエジプトの関係
 | |
エジプト |
日本 |
|---|---|
日本とエジプトの関係(にほんとエジプトのかんけい、アラビア語: العلاقات المصرية اليابانية、英語: Egypt–Japan relations)は、日本とエジプトの間の国際関係である。エジプトの漢字表記「埃及」から日埃関係とも。両国は相互に大使館を設置しており、駐日エジプト大使によって「とても強い友好関係」にあると評価されている[1][2]。現在、この二国は、経済・貿易関係で大きな関係を持っている[3]。
日本は、エジプトは中東の中心的存在になると考えており、エジプトをこの地域内での外交上不可欠な国としてみている[4]。二国の指導者は、中東の和平に関する問題について互いに支援し合っていることで知られている[5]。
二国間には、両国の互いの利益進展の調査を行う協議会を置いている[6]。
2021年時点で、719人の日本国民がエジプトに、1,933人のエジプト国民が日本に在住する[7]。2009年には90,000人の日本人がエジプトを訪れ、2007年には3,500人のエジプト人が日本を訪れた[4]。
結論、エジプトと日本は外交的・国民的にもとても良い親密な関係を築いている。
両国の比較
[編集]| 両国の差 | |||
|---|---|---|---|
| 人口 | 9000万人(2015年)[7] | 1億2711万人(2015年)[8] | 日本はエジプトの約1.4倍 |
| 国土面積 | 100万 km2[7] | 37万7972 km2[9] | エジプトは日本の約2.6倍 |
| 首都 | カイロ | 東京 | |
| 最大都市 | カイロ | 東京 | |
| 政体 | 半大統領制 | 議院内閣制[10] | |
| 公用語 | アラビア語[11] | 日本語(事実上) | |
| 国教 | イスラム教[11] | なし | |
| GDP(名目) | 3307億7900万米ドル(2015年)[12] | 4兆1232億5800米ドル(2015年)[12] | 日本はエジプトの約12.5倍 |
| 防衛費 | N/A | 409億米ドル(2015年)[13] |
歴史
[編集]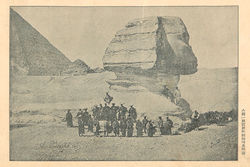
二国間の関係は、19世紀まで遡る。1861年に日本を発った文久遣欧使節は2月20日にスエズに到着し、更に翌1862年に池田筑後守率いる遣仏使節団はフランスに向かう途中の2月23日に、ムハンマド・アリー朝のエジプト太守、イスマーイール・パシャに謁見している[14]。明治維新後の日本にはオスマン帝国、エジプト、ガージャール朝ペルシア(現在のイラン)、エチオピア帝国、アルバニア、タイ王国、清国などと同様に治外法権や不平等条項(カピチュレーション)が欧米列強諸国との間に結ばれており、エジプトには1875年に利害関係各国たるイギリス、フランス、トルコ、イタリア、オーストリア、ドイツなど14か国が個別の領事裁判権をまとめた「混合裁判所」が創設されていたが、箕作麟祥は日本の領事裁判権を問題にする立場からこのエジプトの「混合裁判所」を検討し、1875年1月21日にギュスターヴ・エミール・ボアソナードに対してこの「混合裁判所」制度について質問している他、東海散士(柴四朗)は『埃及近世史』の中で領事裁判と混合裁判所について述べ、原敬は『埃及混合裁判』の中でこの「混合裁判所」がエジプト人よりも欧米人に対して圧倒的に有利な裁定を下していることについて言及している[15]。
1879年にイギリスのソールズベリ外務大臣は駐カイロ総領事に訓令を発し、反イギリス的な政策を採ろうとしていたエジプト副王イスマーイール・パシャを、名目上のエジプトの宗主国であったオスマン帝国に圧力をかけて解任させると、このイスマーイール・パシャ解任事件に憤ったアフマド・オラービー大佐は1881年2月に反旗を翻し、同年9月にアブディーン宮殿を包囲してイスマーイール・パシャの後任となったタウフィーク・パシャに憲法制定を認めさせ、翌1882年2月にオラービー大佐自らが陸相に就任し、民族主義的な祖国党内閣を樹立した(ウラービー革命)[16]。明治時代の日本の東海散士が著した政治小説『佳人之奇遇』にはこのウラービー革命を「一八八二年二月七日、魔毛嫉佐徴主相トナリ、亜刺飛陸軍大臣トナリ、是ニ全ク新内閣ヲ組織シ、同月六日、新憲法ヲ発布ス。是ヨリ五月ニ至ルマデ、国政真正ナル立憲政体トナリ、国民党モ亦漸ク平穏ニ帰セリ[17]」と述べて評価する記述が存在する。
ウラービー革命挫折後、1880年代から1910年代にかけてエジプトではムスタファー・カーミルの指導の下、ウラービーの祖国党(ワタニー)を復興し、エジプトの反英独立闘争が続けられたが、カーミルは1905年の日露戦争の日本勝利の際に、白人に対する有色人種の勝利であるとしてこの日本の勝利を評価している[18]。
他方、日本側ではクローマー総督がエジプトに於けるイギリスの政治的実践について述べたことを1908年に刊行した『現代エジプト』を、1911年に大日本文明協会より日本語訳刊行し、大隈重信は同書の日本語版に寄せた序文にて、イギリスのエジプト経営を日本の韓国保護経営の「経世的教訓」とすべきだと述べている[19]。
1921年4月には訪欧の途次にあった皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)がエジプトに立ち寄り、ピラミッドの見物やムハンマド・アリー朝のスルタン・フアード1世との非公式会談を行っている。
外交関係樹立後
[編集]両国の外交関係は、日本がエジプト王国の独立を承認した1922年に確立された[20]。外交関係樹立以来、第二次世界大戦中を除けば親しい関係が続いており、身分の高い外交官も何度か訪問している。主要なものに、日本の首相・村山富市による1995年のエジプト訪問や、ムバーラク大統領による1983年、1995年、1999年の数回にわたる日本訪問がある[4][21][22]。
1936年1月1日、日本はカイロに公使館を開設し[23][7]、翌1937年に初代公使に横山正幸が任命された[24][25]。しかし第二次世界大戦の勃発により、1941年12月8日付でエジプトは日本に国交断絶を通告した[26]。
戦後の1952年11月、日本とエジプトの両国は国交を回復させ[27]、1954年4月1日に在エジプト公使館は大使館に昇格させた[25]。
1998年から2002年にかけて、日本は35億ドル以上をエジプトに資金提供した[28]。2002年には、日本とエジプトの間の貿易額が1億ドルを超えた[29]。日本は救急車や橋、王家の谷のビジターセンターなどを提供している。
2015年1月17日、エジプトの首都カイロで開催された日エジプト経済合同委員会の席上において、安倍晋三内閣総理大臣は「ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します[30]」と公式に述べて、反ISIL(いわゆる「イスラム国」)およびエジプト支持の姿勢を明確に打ち出した[31]。
外交使節
[編集]在エジプト日本大使・公使
[編集]駐日エジプト大使
[編集]エジプト王国
[編集]| 代 | 氏名 | 在任期間 | 官職名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アブドゥル・ワハーブ・ダウード・ベイ(ニコラス・カリル・ベイ) | 1938年 - 1940年[32] | 特命全権公使 | 信任状捧呈は1月17日[33] |
| サミ・シメイカ | 1940年 - 1941年[32][34] | 臨時代理公使 | ||
| ※1941/12/08 公使館閉鎖~1953/8再開[32] | ||||
エジプト共和国
[編集]| 代 | 氏名 | 在任期間 | 官職名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ※1953/8 公使館再開[32] | ||||
| 1 | オスマン・エベイド | 1953年 - 1954年[32] | 特命全権公使 | 信任状捧呈は9月16日[35] |
| ※1954/04/20 大使館昇格[32] | ||||
| 2 | オスマン・エベイド | 1954年 - 1957年[32] | 特命全権大使 | 信任状捧呈は4月28日[36] |
| Found Mohammed Shebe | 1957年[32] | 臨時代理大使 | ||
| 3 | ムースタファ・ユーセフ | 1957年 - 1958年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は10月23日[37] 日本外交史 |
アラブ連合共和国
[編集]| 代 | 氏名 | 在任期間 | 官職名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オスマン・ファウジー | 1961年 - 1961年[32] | 臨時代理大使 | ||
| 1 | アブデル・ラフマン・エル=アズム | 1961年[32] | 特命全権大使 | |
| オスマン・ファウジー | 1961年 - 1962年[32] | 臨時代理大使 | ||
| イー・アミン・イブラヒム | 1962年[32] | 臨時代理大使 | ||
| 2 | サレ・ハリル | 1962年 - 1968年[32] | 特命全権大使 | 信任状捧呈は12月24日[38] |
| 3 | マハムード・ハサン・エル・アルーシー | 1968年 - 1972年[32] | 特命全権大使 | 信任状捧呈は9月11日[39] |
エジプト・アラブ共和国
[編集]| 代 | 氏名 | 在任期間 | 官職名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マハムード・サラーハッディーン・ハサン | 1972年 - 1973年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は3月1日[40][41] |
| 2 | モホセン・アブデル・カレック | 1973年 - 1979年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は10月29日[42] |
| 3 | サード・アブデル・ファター・ハリール | 1979年 - 1981年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は3月22日[43] |
| 4 | アブデル・ファッターハ・ハッサン・シャバーナ | 1981年 - 1984年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は1月21日[44] |
| 5 | モハメッド・サミ・サーペット | 1984年 - 1988年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は11月7日[45][46] |
| 6 | ワヒブ・ファハミ・エル・ミニアウィ | 1988年 - 1993年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は10月21日[47] |
| 7 | メルバット・メハンナ・タラウィ | 1993年 - 1997年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は10月1日[48][49] |
| 8 | モハメッド・ナビール・イスマイル・ファハミ | 1997年 - 1999年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は9月24日[51][52] |
| 9 | マハムード・カレム・マハムード・モハメッド | 1999年 - 2003年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は9月20日[54][55] |
| アハメッド・ファルーク・タウフィック・ワハビィ | 2003年[56] | 臨時代理大使 | ||
| 10 | ヒシャーム・ムハンマド・ムスタファ・バドル | 2003年 - 2007年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は11月11日[57] |
| サラー・エルディン・アブデル・サデック・アハメッド | 2007年[59] | 臨時代理大使 | ||
| 11 | ワリード・マハムード・アブデルナーセル | 2007年 - 2011年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は10月1日[60] |
| 12 | ヒシャーム・エルズィメーティ | 2011年 - 2015年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は12月5日[61] |
| ラギー・エルエトレビー | 2015年[62] | 臨時代理大使 | ||
| 13 | イスマイル・アハメド・カイラット | 2015年 - 2017年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は5月7日[63] |
| ハーテム・サラ・ハッサン・エルナッシャール | 2017年[64] | 臨時代理大使 | ||
| 14 | アイマン・アリ・カーメル | 2017年 - 2021年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は12月11日[65] |
| カリム・フェクリ・モハメド・モクタール | 2021年[67] | 臨時代理大使 | ||
| 15 | モハメド・アブバクル・サレー・ファッターフ | 2021年 - 2025年 | 特命全権大使 | 信任状捧呈は12月27日[68] |
| サーメ・モハメド・エルデメルダシュ・エルヒシン | 2025年 - [69] | 臨時代理大使 |
脚注
[編集]- ^ Embassy Avenue Index(2011年2月1日時点のアーカイブ)
- ^ http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/bilateral/japan_egypt/recent_progress/2008/index.htm [リンク切れ]
- ^ Al-Ahram Weekly|Economy|Japan and Egypt open up(2014年10月6日時点のアーカイブ)
- ^ a b c MOFA: Japan-Egypt Relations(2012年10月31日時点のアーカイブ)
- ^ Egypt, Japan for delay in Palestinian state declaration, resuming deadlocked peace talks(2013年12月18日時点のアーカイブ)
- ^ Human Exchange and Dialogue Program | Embassy of Japan in Egypt
- ^ a b c d エジプト基礎データ | 外務省
- ^ 平成27年国勢調査人口速報集計 結果の概要 - 2016年2月26日
- ^ 日本の統計2016 第1章 - 第29章 | 総務省統計局
- ^ 日本国憲法で明確に定められている。
- ^ a b エジプト憲法第2条で明確に定められている。
- ^ a b Gross domestic product 2015 | World Bank
- ^ SIPRI Fact Sheet, April 2016 Archived 2016年4月20日, at the Wayback Machine. - 2016年4月
- ^ 岡倉、北川(1993:66-67)
- ^ 岡倉、北川(1993:70-75)
- ^ 岡倉、北川(1993:77-81)
- ^ 東海散士の『佳人之奇遇』の記述については岡倉登志、北川勝彦「第3章 日本とエジプト」『日本 - アフリカ交流史――明治期から第二次世界大戦まで』 同文館、東京、1993年10月15日、初版発行、81頁より重引した。
- ^ 岡倉、北川(1993:88-89)
- ^ 岡倉、北川(1993:89-92)
- ^ The Mainichi Daily News: National Days and Events(2009年5月17日時点のアーカイブ)
- ^ Egypt State Information Service - Egyptian-Japanese ties(2009年2月23日時点のアーカイブ)
- ^ Egyptian-Japanese Relations - Kaoru Ishikawa(2009年6月14日時点のアーカイブ)
- ^ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13091756700、外務省報 第二十一巻(B-外・報21)(外務省外交史料館)
- ^ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13091794600、外務省報 第二十二巻(B-外・報22)(外務省外交史料館)
- ^ a b 在エジプト日本国大使館歴代大使一覧 | 在エジプト日本国大使館
- ^ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04011427300、本邦ニ於ケル学会関係雑件/国際法学会/時局問題特別委員会 第一巻(I-1-3-0-029)(外務省外交史料館)
- ^ 「〔備考〕エジプトとの間の外交関係の回復に関する書簡について」外務省
- ^ Gamal Essam El-Din (2004年11月18日). “Japan and Egypt open up”. Al Ahram. オリジナルの2013年8月27日時点におけるアーカイブ。
- ^ MEO Research Center (2002年6月5日). “EGYPTIAN-JAPANESE TRADE EXCHANGE HITS $1B.”. Asia Africa Intelligence Wire
- ^ 英語での公式発言は "I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL" である。Speech by Prime Minister Abe "The Best Way Is to Go in the Middle" | Ministry of Foreign Affairs of Japan を参照。
- ^ 安倍総理大臣の中東政策スピーチ(中庸が最善:活力に満ち安定した中東へ 新たなページめくる日本とエジプト) | 外務省 - 2015年1月18日
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 鹿島守之助 (1974年). “『日本外交史 別巻3』”. 鹿島研究所出版会. 2025年9月17日閲覧。、p.662-663
- ^ “『官報』第3310号”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 大蔵省印刷局 (1938年1月18日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ “『官報』第3949号”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 大蔵省印刷局 (1940年3月7日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ 『官報』第8013号(昭和28年9月18日付)293頁
- ^ 『官報』第8197号(昭和29年5月1日付)21頁
- ^ 『官報』第9253号(昭和32年10月25日付)596頁
- ^ 『官報』第10820号(昭和37年12月26日付)203頁
- ^ 『官報』第12526号(昭和43年9月13日付)7頁
- ^ “『外務省公表集(昭和四十七年)』”. 外務省情報文化局 (1974年3月1日). 2025年9月17日閲覧。、p.181
- ^ 『官報』第13558号(昭和47年3月4日付)15頁
- ^ 『官報』第14055号(昭和48年10月31日付)15頁
- ^ 『官報』第15653号(昭和54年3月24日付)14頁
- ^ 『官報』第16197号(昭和56年1月23日付)13頁
- ^ 『官報』第17328号(昭和59年11月9日付)7頁
- ^ サーベット大使は、在任中の1985年6月に靖国神社を参拝している。水間政憲『いまこそ日本人が知っておくべき「領土問題」の真実: 国益を守る「国家の盾」』、p.77
- ^ 『官報』第18502号(昭和63年10月25日付)11頁
- ^ “信任状捧呈式(平成5年)”. 宮内庁. 2025年9月17日閲覧。
- ^ 『官報』第1253号(平成5年10月5日付)13頁
- ^ “平成29年春の外国人叙勲 受章者名簿” (PDF). 外務省. 内閣府 (2017年4月29日). 2025年9月17日閲覧。、p.4
- ^ “信任状捧呈式(平成9年)”. 宮内庁. 2025年9月17日閲覧。
- ^ 『官報』第2230号(平成9年9月26日付)12頁
- ^ “令和元年春の外国人叙勲 受章者名簿” (PDF). 外務省. 内閣府 (2019年5月21日). 2025年9月17日閲覧。、p.2
- ^ “信任状捧呈式(平成11年)”. 宮内庁. 2025年9月17日閲覧。
- ^ 『官報』第2715号(平成11年9月22日付)14頁
- ^ “在日エジプト・アラブ共和国大使館・総領事館”. Internet Archive. 外務省. 2003年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “プレスリリース”. Internet Archive. 外務省 (2003年11月10日). 2003年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “令和4年春の外国人叙勲 受章者名簿” (PDF). 外務省. 内閣府 (2022年4月29日). 2025年9月17日閲覧。、p.6
- ^ “駐日外国公館リスト アフリカ”. Internet Archive. 外務省. 2007年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “新任駐日エジプト・アラブ国大使の信任状捧呈について”. 外務省 (2007年9月28日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ “新任駐日エジプト・アラブ共和国大使の信任状捧呈”. Internet Archive. 外務省 (2011年12月5日). 2011年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “駐日外国公館リスト アフリカ”. Internet Archive. 外務省 (2015年4月22日). 2015年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “新任駐日エジプト大使の信任状捧呈”. 外務省 (2015年5月7日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ “駐日各国大使リスト”. WARP. 外務省 (2017年9月27日). 2017年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “駐日エジプト大使の信任状捧呈”. 外務省 (2017年12月11日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ “令和6年秋の外国人叙勲 受章者名簿” (PDF). 外務省. 内閣府 (2024年11月3日). 2025年9月17日閲覧。、p.3
- ^ “駐日各国大使リスト”. Internet Archive. 外務省 (2021年11月9日). 2021年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
- ^ “駐日エジプト大使の信任状捧呈”. 外務省 (2021年12月27日). 2025年9月17日閲覧。
- ^ “駐日各国大使リスト”. Internet Archive. 外務省 (2025年9月12日). 2025年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月17日閲覧。
参考文献
[編集]- 岡倉登志、北川勝彦「第3章 日本とエジプト」『日本 - アフリカ交流史――明治期から第二次世界大戦まで』(初版発行)同文館、東京、1993年10月15日、65-95頁。ISBN 4-495-85911-0。
